こんにちは。
今回は少し時事ネタというか、最近の世間の事件について考察していきたいと思います。
高齢化社会と言われて久しくないですが、年々減りゆく少年少女の尊厳について少し思うところがあるわけでありまして。
これから先長く生きていかなければならない彼らの背中を押す役目を担っているはずの成人が、子供たちを委縮させてしまうような事をしては絶対にいけないですし、自分勝手さながらに現場を私物化するような人たちに子供たちの命を一時でも預ける事はできるでしょうか?
この事件の裏側で一体何が起きたと言うのでしょうか。
甲子園辞退の衝撃――広陵高校で何が起きたのか?
2025年夏の甲子園大会は第107回という数を数える中、広島の広陵高校が初戦に勝利した直後、突然の大会辞退を発表しました。
8月10日に広陵高校の校長が記者会見を開き、公の場で説明していました。
野球ファンだけでなく、教育関係者、多くのお茶の間の人たちに衝撃が走りました。
大会開催中に辞退するという行為は前代未聞、まさに異例の事態です。
その背景には、学校内で起きていたいわゆる暴力事件と、それに対する対応の問題がありました。
過去にも部員の暴力事件がきっかけで出場を辞退した学校もありました。
その事案については大会が始まる前に辞退を決断したようですが、今回は事件が発覚した上で選手は甲子園の土を踏んでいます。
その後、問題がメディアなどに取り上げられると更に状況が激化し、結果的に一回戦終了後「辞退」という結末を迎える事となります。
8月10日、選手を乗せたバスは広島に舞い戻り、その日の夜に保護者らに対して詳細な説明会も開かれたようです。
一体広陵高校では何が起きていたのでしょうか?
暴力事件の発覚まで――隠された真実と告発の流れ
問題の発端はカップラーメン?
2025年1月22日、広陵高校野球部の寮「清風寮」で禁止されていたカップラーメンを食べた一年生も部員が先輩から暴力を受けるという事件が発生します。
この時点でほとんどの人は、え?そんな理由で暴力とか…、と思うと思います。
ただこれは実際にはこの時はじめて起きたという意味ではないと思います。それは過去にも何度か行われていた事でしょう。間違いなく。
暴行の内容は、顔や胸を殴るなど、身体的暴力でした。
学校は内部調査を行ってこの事実を認定しました。加害生徒は謹慎処分となり、2025年3月には日本高校野球連盟(高野連)から「厳重注意」「1ヶ月の公式戦出場停止」処分が下されました。
しかしこの処分は公に公表されていませんでした。
この時点で知っているのは当事者の身内の人たちと一部の学校関係者だけだったでしょう。
更に被害生徒はこの状況に耐えられなくなったため、3月末に学校を転校します。
2025年7月に警察へ被害届を提出しており、事件が民事ではなく刑事事件として扱われる可能性があります。
そして極めつけがInstagramで何者かにより同校の暴力行為のものと思われる動画がアップロードされ、全世界へその事実が明るみに出る事となりました。
SNS時代と言われる現代がみせた、まさに内部告発です。
そして別のSNSにも動画が転載され、さらに過去にいじめを受けていたと名乗る人物が実際の加害者を名指しでSNSへ書き込みをします。
それが行われたのが2025年7月中旬ごろだったと思いますが、その頃からXやFacebookでは広陵高校に対して批難が殺到します。
もはや事態の収拾が困難になったと判断した広陵高校OBは、甲子園の出場を辞退する旨を伝えます。
この時既に甲子園は開幕しておりこのような炎上が起きているさなか、広陵高校は初戦を突破していたという状況。
この告発で行われた内容は、生徒だけでなく、監督・コーチの名前もあったとされます。
全くもって信じがたい事実ですよね。
子どもたちを守る立場にある人が、手を差し伸べるどころかその手が子供たちを傷つけるものであったという末路・・・
私には到底理解する事はできません。
この決断は、学校の対応や隠蔽体質への批判が高まる中での、異例かつ重い選択となってしまいました。
SNS告発と更なる問題について
また今回のSNSでの名指しでの告発に関しては、賛否両論が分かれており、中でも世間からの批判は相当なものとなっていました。
広陵高校の暴力事件がSNSで拡散される中、実名や顔写真を伴う名指し投稿が急増しました。
これに対し、阿部俊子文部科学大臣は2025年8月15日の記者会見で、「冷静な対応をお願いしたい」と呼びかける異例の事態となりました。
さらに、「無関係な生徒や関係者が誹謗中傷にさらされることは決してあってはならない」と述べ、発言のエスカレートが新たな人権侵害を生む可能性を強く警告しました。
SNS告発と人権侵害──正義と暴力の境界線
不特定多数の人々を脅かす存在
このような内部告発は誰もが証拠映像を撮れる現代のスマートフォン社会において非常に有効であるでしょう。
私が高校生だった頃はまだ2000年代初頭で、スマートフォンはありませんでした。
携帯電話を学校に持っていく事など許されるわけもなく、未成年者が携帯電話を持っている事も5:5くらいだったのではないでしょうか?(高校生の話です)
今はどのくらい普及しているのかと言えば小学生ですらスマートフォンを持っている時代と言われます。
正直SNSは、個人が声を上げる手段として非常に有効だと思います。
今回の事件も、被害者の告発がなければ、学校の対応が公になることはなかったかもしれないですし、悪が野放しになるよりかはましな結末だったのかもしれません。
しかしその一方で、「正義の名のもとに行われる暴力」が、別の形で人を傷つける危険性もあるのです。
特に未成年が関わる問題では、実名や在籍情報の拡散は、本人だけでなく家族や周囲の人々にも深刻な影響を与えます。
「暴力は許されない」という思いが、感情的な非難や集団的な攻撃に変わってしまうと、それはもう別の暴力と化してしまうのです。
私もXやInstagramなどはほぼ毎日見ていますが、中には過激な内容の動画が確かにあります。
近年多いのはあおり運転ドラレコの映像や、火事や地震などの瞬間を捉えた映像、強盗などの犯人を捉えた防犯カメラの映像などです。
これらの情報は当事者、加害者が映っているだけでなく、不特定多数の第三者が映っています。
彼らはもちろん人権を持っており、そんな彼らの人権を守るために今回のようなSNS内部告発が悪用されてはいけないという事でもあるのです。
更に一部の過激派の人たちの投稿には、「犯罪者に人権なんかないだろ」「●ズは社会に出てくるなよ」「親がまともな育児をしないから」などと言った文面も平然と見られます。
もちろんそれが間違っている、合っているという正当な判断を私がするわけにはいきません。
それはこれから我々が、社会を担っている大人たちが判断していかなければならない事だからです。
阿部文科相の発言は、単なる注意喚起ではなく、教育現場と社会全体への問いかけでもある。 「子どもたちを守る」とは、加害者・被害者の区別を超えて、冷静で公正な対応をすることなのかもしれません。
ただ一つ言える事は、我々人間は「悩み」「考え」「お互いに共生しあう」生命体です。
その能力が備わっているにも関わらず考える事を放棄し、戦争によって実力行使で他人を貶めたりしてはいけないという事です。
それだけは絶対にしてはいけません。
地球を支配する人間が暴走してしまったら、誰も我々の戦争を止める者はいなくなってしまう。
そこだけは肝に銘じておかなければならないのです。
個人的に思うこと
人助けをする人は、何のために人助けをするのでしょうか?
私はそれを考えた事が何度かあります。
人間は己の満足感を高めるために色々な行動をする生物ですから、
その行動の中に他人を貶める行為が含まれてませんか?という事です。
人を助ける事で、救われる人がいる、救った事で感謝される人がいる。
これは支援者(または援助者)と被援助者の関係です。
しかしこの関係の中で例えば相手が嫌がる事をしてしまった場合はどうでしょうか?
それは、加害者と被害者になります。
何が言いたいかと言うと、今回の事件に関して、加害者はなぜカップラーメンを食べていた後輩に暴力をふるってしまったのか?
という事です。
もしかして加害者は暴力を振るっている事が「教育」だと思っていたのではないでしょうか?
もっと言えばそれがその後輩を助ける目的であるとすれば・・・
事態は客観的観点から検証する必要があります。
なぜカップラーメンを食べる後輩に暴力を振るってやめさせたのか?
その理由が「ルールだから」というのはもはや理由ですらありません。
それは論外です。
ルールがおかしいんですよ?という指摘がなぜ上がらないのでしょうか?
私はまずそこが「?」です。
カップラーメンくらい食べていいと思うんですけどね。
だって高校生ですし。
ましてや運動部でお腹の空く時期の子どもに対して制限を掛けるのは良くないですね。
それによって精神が弱くなる、意思が弱くなるというからという意見については、切り返し方に問題があると思います。
意思が弱くなるかどうかは本人の問題であり、ルールによって全員意思が強くなるのか?といった話ではないと思います。
そんな理由だけで禁止ルールを増やし、暴力事件の発生を助長するかのような束縛する環境になっている事に問題があると、まずはそこに目を向けるべきではないでしょうか?
それが、伝統を重んじるだとかそういった他力的理由で片付けてしまうのはそもそも教育をしているのでしょうか?
学校とは一体何なのでしょうか?
そこを今しがた、再考する時期に来ているのではないでしょうか。
教育とは?モラルとは?──子どもたちを守るために必要なこと
今我々が直面しているのは、甲子園大会の在り方とかそんな話ではありません。
この問題が求めているのはもっと大きな問題です。
それは教育の在り方についてです。
学校という名の世界
私も高校時代、全寮制の高校に通っていました。
寮生活というのは、学生という同じ立場の人間が同じ場所で暮らす事を指していますが、そのような閉塞的な空間に同じ年ごろの少年たちが生活を共にすると何が起きるのか?
…という事だと思います。
どういう事かと言うと、人間も一つの派閥を形成し、それが組織化していき、やがては階級社会のような構造が出来上がっていくのです。
それは誰かが主導しなくても、自然に成り立っていくのです。
私もかつて全寮制で暮らしていましたし、実際先輩は後輩を手下(悪く言えば奴隷的)のように扱っていたように思います。
確かにそのような階級社会という構造はありました。
いわゆる「仲間意識」とか「絆」が美徳される一方、それが沈黙の圧力であったり、同調の強制を悪いようにひっぱり出してしまう可能性を孕んでいるです。
まだこの世に生を享けて数年、十数年しか経っていない人間が全く価値観の違うかもしれない人間たちと同じ教室の中で一日の半分ほどの時間を過ごすその難しさ。
それは皆さんも分かっているのではないでしょうか?
私も中学校時代、ほとんど学校に行けませんでした。
学校に行けば、真面目君滑稽だね、と嘲笑され、友人と呼べる存在はみな利用してくる側でした。
学校に行かないようになって、客観的にその空気を見た時、人は初めて自分の立ち位置を理解する事ができるのです。
その現実がいじめの対象であるならば、もはや学校で共同生活をする事はできないでしょう。
孤立してしまった人間は、派閥から切り離され、取り残されて、やがていじめという淀んだ空間の中で自らの心を汚されていくのです。
私はかつて、彼らと同じ被害者でした。
だから今ここでその事についてお話したのです。
道徳に関すること
学校の授業には「道徳」という科目があると思います。
道徳とは、個人や社会が共有する倫理的な価値観や行動基準を指し、学校教育においては、子どもたちが善悪を理解し、他者を思いやる心や社会に対する責任感を育むための重要な要素です。
道徳教育は、子どもたちが自分自身の行動を考え、正しい選択をする力を養うことを目的とし、友人や家族、地域社会との関係をより良いものにするための基盤を築く役割を担います。
しかし我々が学校で教わっているのは、教師と言う名の人間であり、彼らは赤の他人です。
人として、本当に大切な事は、血の繋がった親から教わる事でしか身に沁みないのです。
SNSなどで無責任な発言を繰り返す人たちは、道徳のどの字も備わっているとは思えないです。
それが結果的に他人を平気で傷つけたり、殺めてしまったりする事に繋がっていくのではないでしょうか?
道徳とは、血の繋がった親から教わるもの。
私はそう思います。
ましてや昨今、平気で離婚を繰り返したり、実の親とも離れてしまっている家庭が多い実状も納得ができません。
なぜそのような身勝手な事ができる人がいるのでしょうか?
子どもたちの気持ちを考えた事はないのでしょうか?
子育てする気がないのでしたら、子どもを作らないでください。
そんな無責任な大人が増えたから、子どもはまともな教育を受ける事が出来なくなっているのではないのでしょうか?
この事件の真の被害者は子どもたちかもしれません。
競争主義的野球はもうやめるべき?
最後に野球という競技の在り方についても目を向けたいです。
甲子園という舞台が「伝統」や「勝利」を重んじるあまり、高校生が野球を楽しむという本来の姿が見失われていないでしょうか?
もう私はこれが気掛かりで仕方ありません。
野球を楽しみたい人たちが野球部に入って先輩から暴力を振るわれるのでは、子どもたちが持つ自由な発想やアイデア性、可能性を潰してしまう事になってしまいます。
それでいいのでしょうか?
絶対よくないでしょう。
スポーツは本来、成長や喜び、仲間との絆を育む場であるはずです。
勝利至上主義が暴力や隠蔽を生むなら、それは教育ではなく、ただの競技管理でしかありません。
悪人生成機と言ってしまっても言い過ぎではないと思います。
そんなお零れ的な楽観主義者は空き地で草野球でもしてろ、と言われそうですが、そもそも逆に競争主義の野球を主権に捉えてスポーツの活気が良くなっていく事があると思いますか?
野球部に入った選手はみな丸坊主にするという習慣が日本にもごく最近まで存在していました。
未だにそれを強制している学校もあります。
一体何のため?誰のためにそのような事をしているのでしょうか?
私は逆に狂信的な暴力的概念がそこに居座っているとしか思えません。
そこにスポーツを楽しむ心など、微塵も感じられませんし、甲子園球場で笑顔でプレーしている選手などほとんど見た事がないのもそのせいではないでしょうか?
この事件を通して、私たちが考えるべきなのは、子どもたちの心をどう守るかということです。
制度や伝統に縛られるのではなく、一人ひとりの人間としての尊厳を大切にする教育が、今こそ求められているのではないでしょうか。
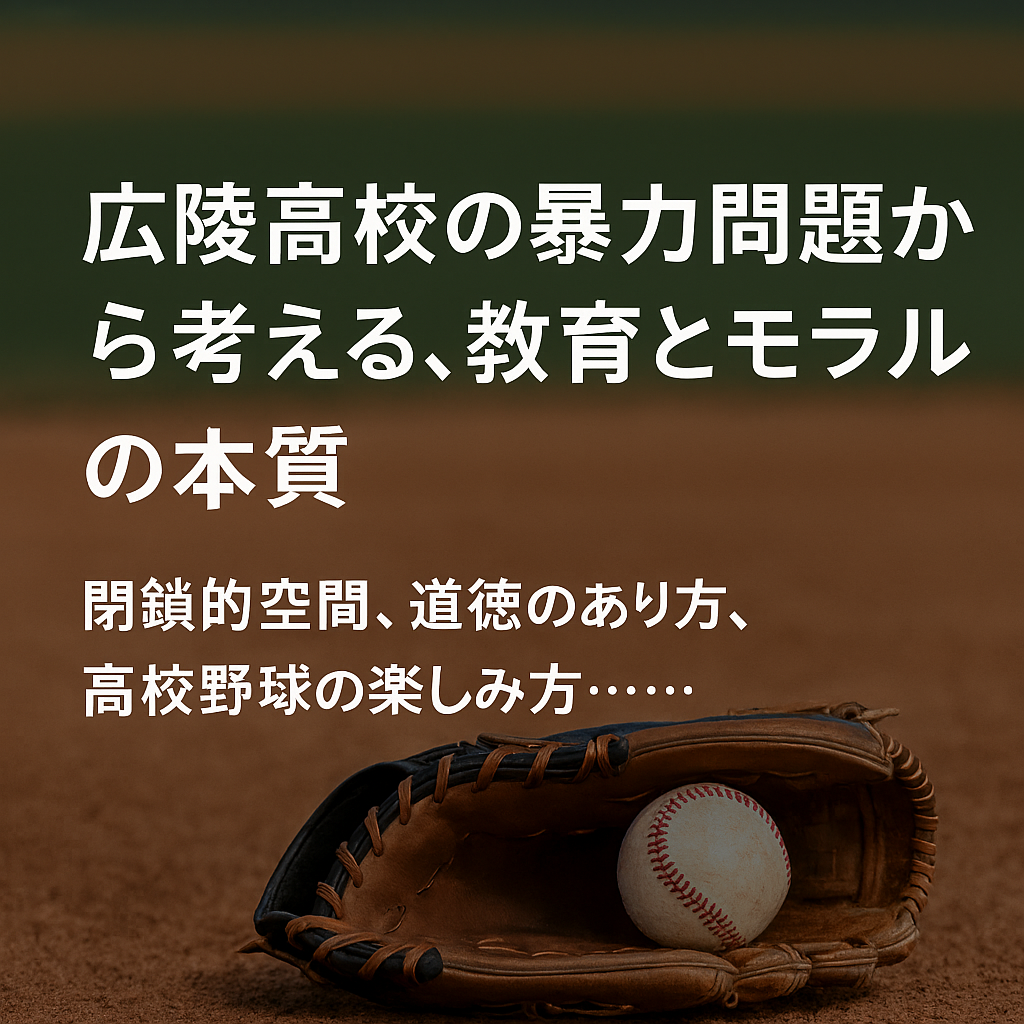
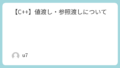

コメント